特別講演 民間の生涯学習推進を考える」 香川大学教授 清國 祐二 氏
- lliskagawa
- 2017年4月15日
- 読了時間: 2分

香川大学生涯学習教育研究センター長・教授
清國 祐二 氏に講演していただきました。
「民間の生涯学習推進を考える」
Ⅰ、考え方によって生き方が大きく変わる。
島根県海土町のスローガン「ないものはない」
全てあるのかないのか、言えるような観光資源がない。ないところに価値を見出す。
発想の転換が大事。
Ⅳ、家庭教育も地域の教育力もどちらも大切
民間指導者への期待①
<未来を託する子供の教育への責任>
地域の中で学ぶ機会を作っている。地域の方にも「責任」を負ってもらう。評論家ではいけない。
民間指導者への期待②
「人づくり・絆づくり」に向き合う、「しがらみ」「お節介」への回帰?
→ミッション(使命)が大事
Ⅴ、豊さと幸せは必ずしも一致しない
「豊かさ=幸せ」でしようか?
物理的豊かさによって人間の本来の力が失われてきた。取り戻すための努力が必要
教育に「回復」の機能を付与する。「回復」が幸せにつながる。
「回復」の機能をどう担うのか?地域と家庭がその役割を担う。
Ⅵ、ある時代だからこそ難しい? 損得勘定も要注意?
損得勘定がはびこれば地域は滅びる。
「得」だけでは成り立たない。小さな「損=役割」を引き受けてやっと大きな得がうまれる。
「ある時代」の社会教育・地域社会
山頂しか知らない子供・・・麻痺した大人。維持するか転げ落ちる
→過程や苦労、作業を知らない。経験の欠如、乏しい想像力。全世代に蔓延しつつある。
豊さ・与えられる時代は終わった。地方、地域から「ほころび」が始まる。
→限界集落や消滅集落への危機感。集落も市場原理に晒されている。
Ⅶ、コーディネーターとコミュニケーション・・密接な関係
行動原理の理想像、「正義・信念」が理想的(欧米流)、しかし、私たちは
行動原理の実態は「関係・役割」では
地域の仕組みは、コーディネーターとコミュニケーション
「優しさ」「穏やかさ」「思いやり」相手の立場で考えられる人。ためになる人、役立つ人。
ひとまず「聞き上手な人」
①笑顔が多く、相槌が上手な人
②最後まで「聴いて」くれる人
③関心を以って「訊いて」くれる人
まとめにかえて
「民間」特にボランタリーな活動の難しさ、変わりがいない、見つけるのが困難。
→ミッションは熱意で支えられている。
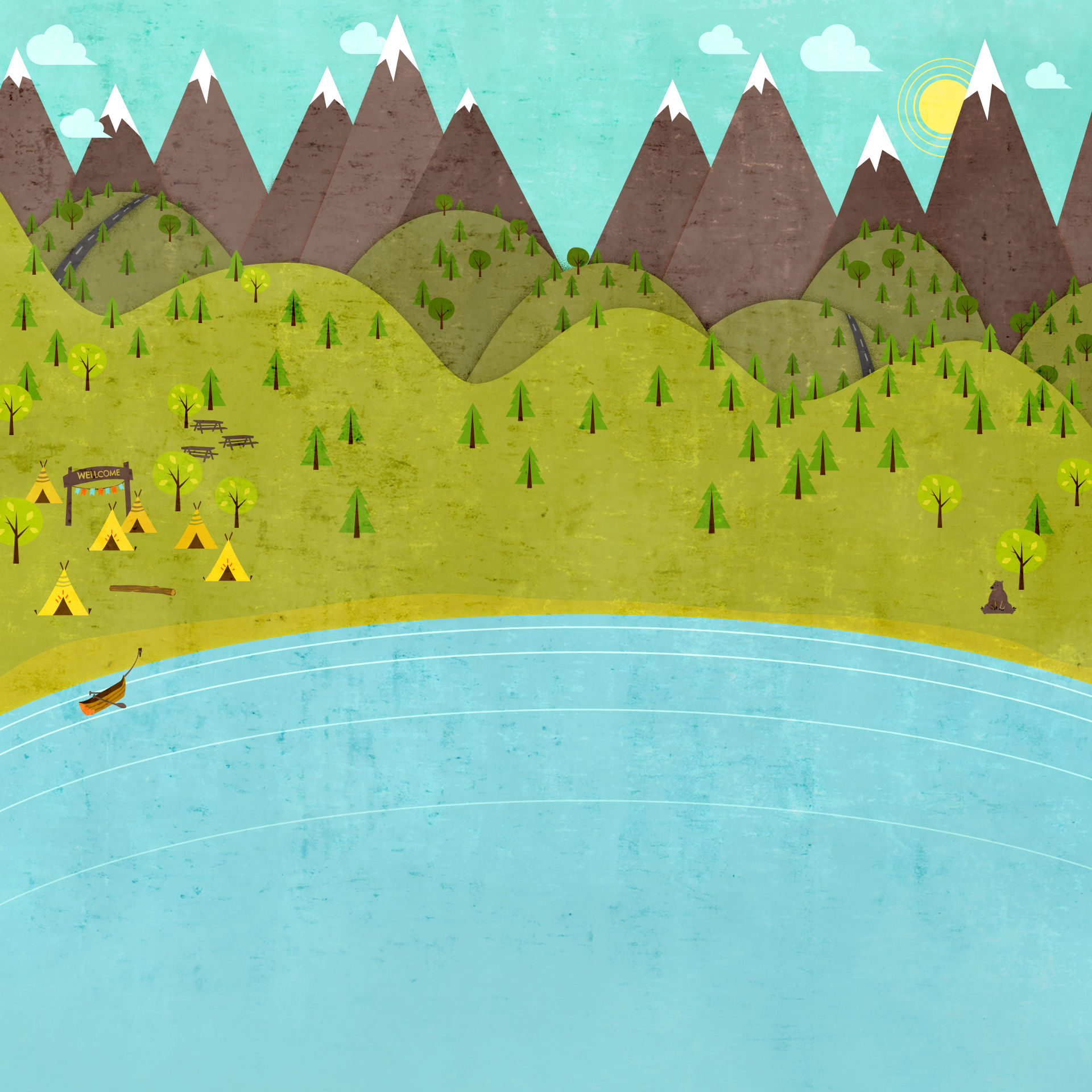
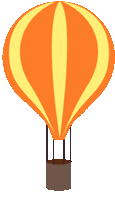
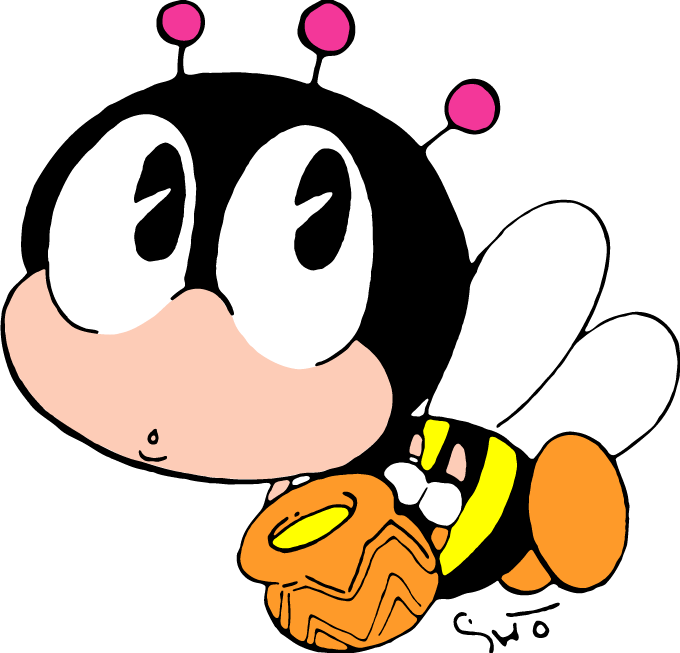
























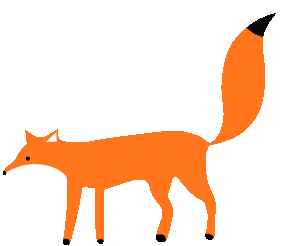
Comments